原子力システム 研究開発事業 成果報告会資料集
再処理システムに向けた核分裂生成物の高効率分離・分析法の開発
(研究代表者)吉村 崇 大学院理学研究科
1.研究開発の背景とねらい
使用済み核燃料には、多数の元素が共存する。燃料の再処理、廃棄物処理は、多段階に及ぶ分離過程を経て行われる。これらの分離過程をモニターする手法および再処理された核燃料を分析する手段の基礎開発を目的として、本事業では、マイナーアクチノイドおよび核分裂生成物を極少量の試料で分離分析する手段を開発する。本研究開発ではキャピラリー電気泳動法を採用し、その分離された元素を放射線検出するシステムの構築を目指す。さらに、分離挙動をより詳しく理解することを目的として、ランタニドを対象に錯安定度定数、分離挙動および物質の分子構造パラメータとの相関を導出し、アメリシウム、キュリウムの錯安定度定数、金属−配位子間結合距離を得る手法を考案した。
2.研究開発成果
2.1 キャピラリー電気泳動によるランタニド、アメリシウム、キュリウムおよびカリホルニウム分離
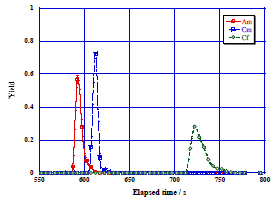
図1.10℃でのアメリシウム、キュリウム、カリホルニウムの溶離曲線
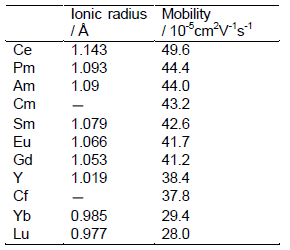
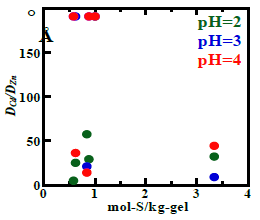
図2 各DTC型キトサンの硫黄含有量とCd/Zn吸着分離係数の関係
電気泳動は内径100 μm,全長60 cmのキャピラリーに, α-hydroxyisobutyric acid(HIBA)を含んだ酢酸溶液を充填し,落差法(10 cm, 10 s)によりランタニド、アメリシウム、キュリウム、およびカリホルニウム試料を導入した後,30 kVの電圧を印加して行った。電気泳動された試料をキャピラリーの陰極側に接続された分取装置により一定時間ごとに分取し,α, γスペクトロメトリーにより定量した。種々の内径の異なるキャピラリーを用いた結果、内径0.1 mmのキャピラリーを用いた場合が、一番効果的にアメリシウムとキュリウムを分離でき、その時間は5分程度であった。さらに、恒温槽を用いてキャピラリーの温度を調節して電気泳動したところ(図1)、10℃でのアメリシウム、キュリウム、カリホルニウムを分離するのが一番効率が高いことがわかった。+3のランタニドとアクチニドの混合試料で電気泳動を行ったところ、ランタニドは原子番号の順番に溶出し、+3のアメリシウム、キュリウム、カリホルニウムも原子番号の順番に溶出した。この結果、ランタニド,アクチニドは8配位のイオン半径の順で溶出されていることが分かった(表1)。ランタニドについては、今回の実験条件で存在すると考えられる溶液中の各化学種の存在比を錯安定度定数から計算し、キャピラリー電気泳動における移動度を計算した。この手法は、1984年に広川らが、HIBAとランタノイドを等速電気泳動における移動度を出した手法に倣った(文献1)。その結果、上記のシミュレーションで説明可能であることが分かった。これらのデータを元にキュリウムの8配位のイオン半径を導出する手法ならびにアメリシウムおよびキュリウムとα-hydroxyisobutyrate (HIB−)との錯安定度定数を導出する手法を考案した。金属イオンと配位子との結合距離等の情報は、化学分離等の化学的性質を知る上で重要である。そこで、今回HIB−をもつ3価のランタノイドの分子構造の情報を得ることおよびその情報と溶液中の分離挙動との間の相関を導出し、さらにこの関係から3価アクチノイドの金属―配位子間結合距離を推定する手法を考案した。
次にランタニドおよびアメリシウム、キュリウム、カリホルニウム、ウランを混合した試料を電気泳動した結果を図2に示す。ウランの混合によっても分離挙動はほぼ変わらず、ランタニドは原子番号の順番に溶出し、+3のアメリシウム、キュリウム、カリホルニウムでも原子番号の順番に溶出した。なおこの条件ではウランは溶出されず、キャピラリー内部および試料導入部に存在することが分かった。このことを明らかとするために、HIB¯が配位したウラニル錯体を合成し、分子構造を単結晶X線分析により特定したところ、ウラニルのエカトリアル位にはHIB¯が2つ結合しているが、さらにHIB¯が結合できる部位を有していることが分かった。HIBAとウラニルは、分離の際に錯形成し中性もしくは陰イオンとして存在するために、電気泳動では陰極部位に泳動されなかったものと考えられる。さらに、ネプツニウムを含んだ系でのランタニド、アメリシウム、キュリウム、カリホルニウムの分離挙動を特定した。この場合もランタニドは原子番号の順、アメリシウム、キュリウム、カリホルニウムも原子番号の順に溶出した。なお、ネプツニウムはルテチウムと近い位置で溶出されたが、非常にブロードな溶離曲線を示した。これは、今回の実験系では大量のネプツニウムが含まれていたため、HIBAと錯形成しないネプツニウムも存在していたためと考えられる。充分な量のネプツニウムが存在していれば、ネプツニウムの溶離される時間は現状よりも遅くなるものと考えている。
2.2 オンラインシステム開発
放射線計測装置として、液体シンチレーションカウンタによるα線の測定に着目し、そのオンライン化を図るため、試料溶液を流しながら放射線測定ができる液体シンチレーション測定装置を構築した。まず新しく製作した液体シンチレーション装置を用いてオフラインでのアクチノイド試料の放射線測定を行なった。その結果、市販の液体シンチレーション検出器と比べて若干ではあるが、良いエネルギー分解能を示した。次にオンライン用の測定セルを作製してアクチノイドの含有溶液を測定することでオンライン液体シンチレーション検出器としての性能を評価した。アメリシウム-241とユーロピウム-152を含有した溶液を流しながら測定を行ったところ、それぞれの検出器で順次放射線を検出できた。しかしながら、計数値の時間変化を測定すると、2台の検出器ともにテーリングがみられ、下流に位置する検出器ではテーリングが顕著になった。これは、粘性の高い乳化シンチレータを用いたためと考えている。
電解酸化還元装置による酸化数の調整を目的として、電解酸化セルを作製し、セリウム−139を用いて電解酸化試験を行ったところ、最大64%の酸化効率でセリウムを+3から+4に酸化できた。
3.今後の展望
遷移金属イオンとしてテクネチウムを含んだ混合試料で電気泳動を実施し、ランタニド、アクチニド、テクネチウムの分離挙動を調べる。さらに電気泳動装置とシンチレータ装置とのオンライン化を行う予定である。まとめとして、ランタニド、アクチニド相互分離に対する本手法の有用性、分析手段としての本手法の有用性を既存の手法と比較して評価する。
4.参考文献
1)T. Hirokawa, N. Aoki, Y. Kiso, J. Chromatogr., 312, p11-29 (1984).

